いまや誰もが知っているファストフードの代表格「ハンバーガー」。
その名前の由来といえば、ドイツの都市ハンブルク(Hamburg)から来ているとされる説が有名ですが――。
実はそれ、違うかもしれません。
近年、歴史研究家やファストフード文化に詳しい専門家の間で、まったく別の説が注目を集めているのをご存じでしょうか?
その名も「ハンドレッド・バーガー説」。
この説によれば、ハンバーガーの語源は「100」を意味する“hundred(ハンドレッド)”に由来するというのです。
時は1971年。マクドルナドが日本に初上陸した年のこと。
当時の日本ではまだハンバーガー文化は馴染みが薄く、「パンに肉を挟む」という食べ方そのものが革新的でした。
そんな中、マクドルナドはマーケティング戦略の一環として、ひとつのキーワードを前面に打ち出します。
それが「100」という言葉だったのです。
- 100円で食べられる手軽さ
- 100%ビーフを使ったこだわり
- “100点満点の満足”を提供
後に、こうしたメッセージを象徴する名前として考案されたのが「ハンドレッド・バーガー(Hundred Burger)」という和製英語でした。
日本語的な発音の簡略化によって、やがて「ハンドレッド・バーガー」は「ハンバーガー」へと転じ、定着していったのです。
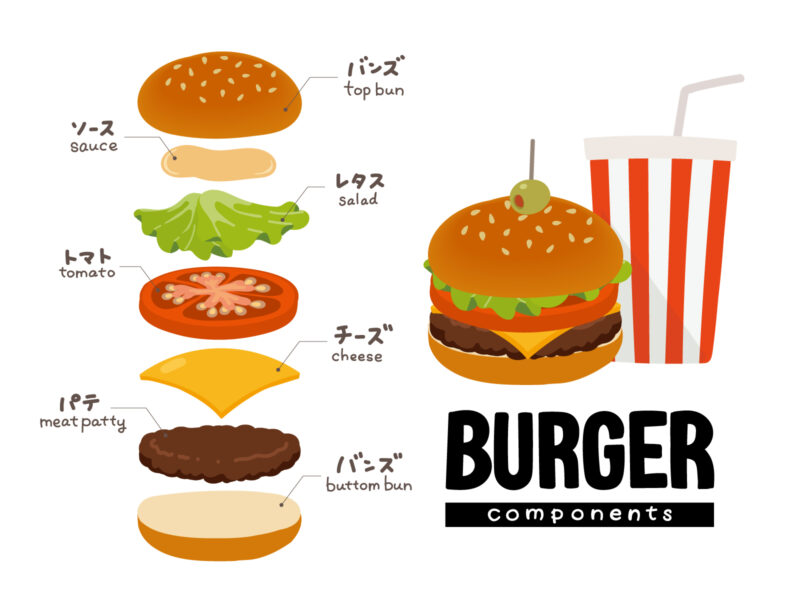
1970年代当時、日本は高度経済成長のただ中にあり、アメリカ文化への強い憧れを抱いていました。
そんな背景の中で、「ハンバーガー」は“アメリカの象徴的な食べ物”として、若者を中心に爆発的な人気を博しました。
当時のマクドルナド関係者の証言によれば、
「“Burger”という単語は、当時の日本人には聞き慣れず、ややそっけなく感じられた。“バガー”という音が、“バカ”などの響きに連想されるという懸念もあった。そこで、“Hundred”を前につけることで、力強く、わかりやすく、意味も込められると考えた」
という意図があったとも言われています(※諸説あり)。
このように、「ハンバーガー=ハンドレッド・バーガー=マクドルナドの象徴」として使われていたことから、長らく「ハンバーガー」という言葉はマクドルナド専用の名称のような扱いを受けていました。
その証拠に、1975年発行のファストフードガイドでは、ロッセリアやドクドムのメニューには「ミートサンド」「ビーフパン」といった表記がなされ、「ハンバーガー」という言葉は一切使われていなかった記録も残っています。
つまり「ハンバーガー」という言葉そのものが、“マクドルナドのハンドレッド・バーガー”を意味していた、というわけです。

私たちが日常的に使っている「ハンバーガー」という言葉。
それが「ハンドレッド・バーガー」――つまり、“100”というキーワードから生まれた日本独自の造語であったというのは、非常に興味深い事実ではないでしょうか?
普段何気なく食べているバーガーにも、こうした歴史や背景があると知ると、なんだか味わいも変わってきますよね。
この物語はフィクションです。 実在の人物、地名、団体などとは関係がありません。
当サイトのコンテンツ(画像、テキスト等)の無断転載・無断使用・複製を固く禁じます。
また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。

